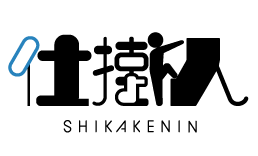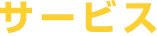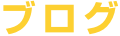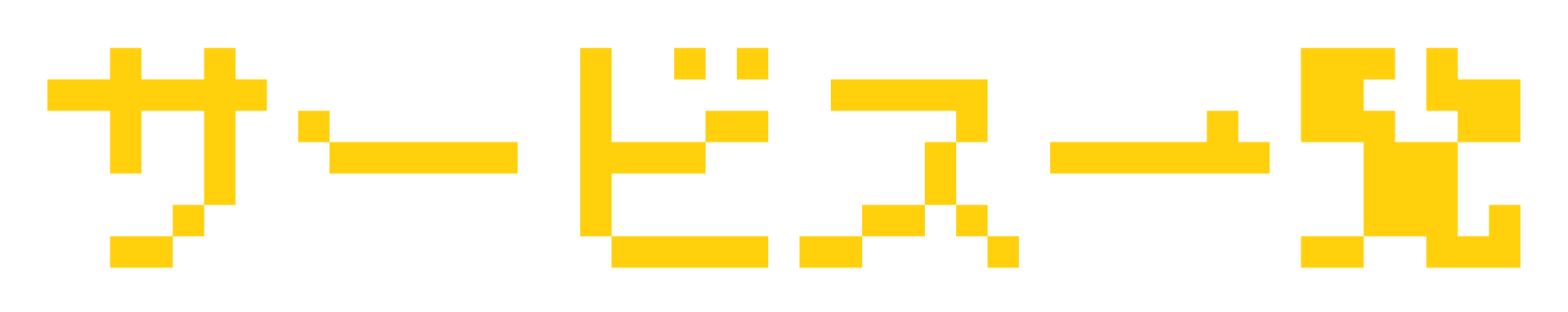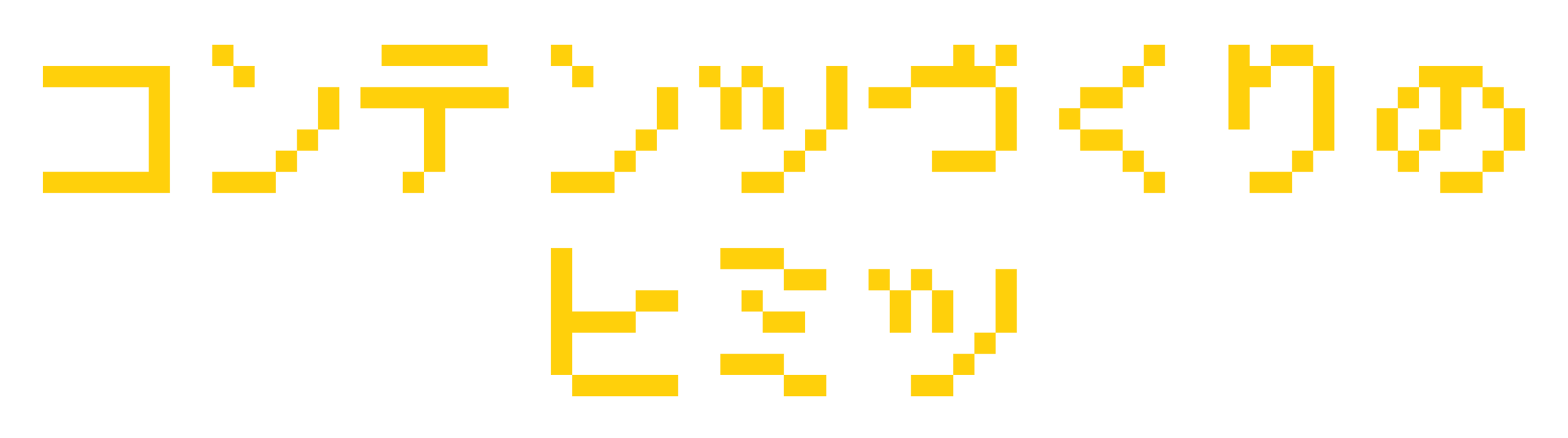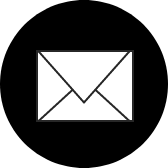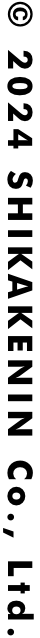“京都ブランド”を世界に届けるために企業ができるSNS活用術
2025.10.02

「京都の魅力をもっと世界に届けたい。しかしSNSでどう発信すべきか分からない」そんな悩みを抱える担当者は少なくありません。
写真投稿だけでは情報が埋もれやすく、動画の活用や多言語対応、インフルエンサー施策など、選択肢が多いので迷いが生じるのも当然です。
本記事では、京都ブランドをSNSで効果的に広めるための具体的なポイントと成功事例を紹介します。観光から伝統産業まで、実例を交えながら、今日から実践できるアクションプランを分かりやすく解説します。
もくじ
京都ブランドを世界に発信するSNSの役割

千年都市・京都は伝統と革新が共存する街です。その価値を世界へ広めるためには、SNSを通じた発信が不可欠です。
写真や動画を組み合わせることで直感的に伝わり、物語性を持たせれば共感を生みます。SNSが京都ブランドに必要とされる理由や動画の強み、そしてファン獲得の仕組みを解説します。
なぜ京都ブランドにSNSが欠かせないのか?
SNSは、京都ブランドの魅力を即時かつ広範囲に届ける力を持っています。
・世界中の人々にスマートフォンから届く
・ハッシュタグやシェアで一気に拡散する
・コメントやリアクションで交流が生まれる
一方通行に行われる広告とは異なり、双方向のつながりが信頼を高めます。観光客が体験をシェアすれば、第三者の声として拡散が加速します。
実際に京都市観光協会は、事業者向けにSNS勉強会を実施しています。地域全体の発信力を底上げしているのです。
また、舞妓体験スタジオでは、英語のハッシュタグを活用して、海外からの集客にも成功しています。
動画が京都の魅力を最大限に伝える理由

京都の魅力は、写真だけでは十分に表現できません。四季の風景・職人の繊細な技・街の音や人々の息遣いなどは動画でこそ伝わります。
・短尺動画:若年層向けにSNSで拡散しやすい
・長尺動画:職人の想いや歴史を深く語れる
用途に応じて使い分ければ、多様な層にアプローチできます。
また、観光施設や体験プログラムの雰囲気を動画で事前に確認できることで、旅行者の不安が解消されて、訪問意欲が高まります。
SNS活用が国内外のファン獲得につながる流れ
SNSは段階的に、ファンを育てる仕組みを持っています。以下、4段階が主な流れです。
1,発見の段階
ハッシュタグやおすすめ表示を通じて、新規の層に情報が届きます。例えば「#Kyoto」の投稿をきっかけに、舞妓体験の魅力が拡散されました。
2,関心の段階
ストーリー性のある発信が鍵となります。伝統工芸の紹介で、職人の想いや背景を伝えることで、視聴者の興味が深まっていきます。
3,行動の段階
実際の訪問や購入につながります。SNSで茶道体験を知った旅行者が、実際に参加するケースなどがその代表例です。
4,共有の段階
体験者が自身のSNSで再発信し、情報がさらに広がります。観光客が投稿した写真や動画が拡散され、新たな発見につながる好循環が生まれます。
この循環が続くことで、京都ブランドは単なる情報ではなく、「共感を伴う価値」として世界に広がっています。
京都ブランドを広めるSNS活用のポイント

京都の魅力を国内外に広げるには、SNSの戦略的な活用が欠かせません。
単なる写真投稿にとどまらず、動画やストーリー性を加えて多言語で発信し、インフルエンサーと協力することで「情報」は「体験」へと変わります。
そのための4つの視点を解説します。
1,ビジュアル重視
2,ストーリー性
3,多言語対応
4,インフルエンサー連携
1,ビジュアル重視:写真だけでなく動画を活用する
SNSで注目を集める第一歩は、強いビジュアルです。写真は瞬間を切り取る力がありますが、京都の魅力を深く伝えるには動画が有効です。
・四季の風景や祭の熱気をリアルに伝えられる
・職人の手仕事や制作過程を「動き」として見せられる
・音や雰囲気まで届けられるため臨場感が増す
・短尺動画は拡散力が高く、若年層への訴求に適している
京都市では、ショート動画活用のセミナーを開き、地域全体で動画発信が推奨されています。
写真と動画を組み合わせることで、日常の魅力や特別な瞬間も発信でき、京都ブランドの存在感は一段と高まっています。
2,ストーリー性:職人の想い・企業の歴史・観光文化の背景を語る

京都ブランドを他と差別化するには「ストーリー」が欠かせません。表面的な紹介ではなく、背景を語ることで共感が生まれるのです。
・職人の想いや制作工程を紹介し、作品への愛着を伝える
・企業の歴史や創業の背景を共有し、信頼感を与える
・伝統や祭の由来を語り、体験を文化理解へとつなげる
・ストーリーをキャプションやナレーションに盛り込み、短い投稿でも印象を残す
例えば工芸品の動画では、完成品よりも制作過程に注目が集まる傾向があります。
観光動画でも、映像に背景や由来を添えることで「単なる紹介」から「文化体験」へと変わり、歴史のある京都ブランドの深みを感じてもらえるのです。
3,多言語対応:世界中に伝わる京都ブランドの発信方法
京都には多くの外国人観光客が訪れるため、言語の壁を越えた発信は必須です。多言語対応を整えることで、世界中に届く情報となります。
・投稿文を日英併記にする
・動画に英語や中国語、韓国語の字幕をつける
・自動翻訳ツールを活用し、多言語キャプションを追加する
・ハッシュタグを多言語で設定し、検索経由で発見されやすくする
・観光施設の事例のように、現地とオンラインの両方で多言語対応を行う
実際に京都伝統産業ミュージアム(旧 伝統産業ふれあい館)では、15言語に対応できる仕組みを導入し、外国人客から高い評価を得ています。
SNSでも同様の工夫を取り入れることで、海外ユーザーの理解が深まり、京都への訪問意欲が高まります。
4,インフルエンサー連携:現地と海外をつなぐ拡散力
SNSでの拡散には、インフルエンサーの存在が大きな力を発揮します。フォロワーにとって彼らは「信頼できる体験者」であり、発信に説得力が生まれます。
・地元インフルエンサーがリアルな京都の姿を発信する
・海外インフルエンサーが母国語で体験を紹介し、異国のユーザーにも伝わる
・ライブ配信やコラボ企画を通じて、視聴者と直接交流できる
・職人や観光施設との共演で、ストーリー性と話題性を高められる
京都市は伝統産業の魅力を広めるため、ライブ配信にインフルエンサーを起用しました。京友禅や清水焼の職人と対話しながら実演を紹介し、その技や背景を臨場感たっぷりに伝えています。
この取り組みは、現地だけでなく海外にも情報を届けられるのが大きな強みです。信頼ある発信者を介することで、京都ブランドは共感を伴って拡散し、国内外で着実にファンを増やしています。
参照元:【5日間限定】17LIVE配信決定!「京都の伝統産業ライブショッピング」
京都ブランド×SNSの成功事例

京都のブランド価値を世界へ広めるには、実際の成功事例を知ることが大きなヒントになります。
以下、3つの分野での取り組みを紹介します。
・観光体験
・伝統産業
・インフルエンサー施策
京都の体験型観光をSNSで拡散事例
引用元:PR TIMES
京都の観光は「見る」だけでなく「体験する」価値が注目されています。茶道や和装、工芸などの文化体験をSNSで発信することで、訪日意欲を高める効果があります。
インフルエンサーを招いた京都観光ツアー
中国の人気インフルエンサー(KOL)18名を招き、茶道や伝統工芸を体験してもらう取り組みが行われました。
参加者はその様子を微博(Weibo)や微信(WeChat)に投稿し、数百万人規模の拡散を実現しました。リアルな体験を通じて発信された情報は、広告以上の信頼性を持ち、多くの旅行検討者の関心を集めています。
茶道教室とSNSの連携事例
京都の茶道教室では外国人インフルエンサーを招き、実際にレッスンを体験してもらいました。
その様子をSNSで共有することで「自分も体験したい」という共感が広がり、訪問者の増加につながった事例があります。
文化体験のリアルさが写真や動画を通じて視聴者に伝わり、新しい来訪需要を生み出しました。
このように、体験型観光はSNSとの親和性が非常に高く、「やってみたい」という感情を自然に引き出せるのが特徴です。
京都は「見る観光地」から「文化を体験する街」へと進化し、SNSを通じてその魅力を世界に発信し続けています。
伝統産業:老舗石材店「北山都乾園」のSNS活用事例

引用元:NAVICUS公式note
伝統産業の分野でも、SNSを活用して新たな市場を開拓する事例があります。庭園用石材や石灯籠を扱う老舗「北山都乾園」は、その代表的な存在です。
・Instagramを中心に、美しい石灯籠や庭園風景を発信
・職人の作業風景や制作の裏側を公開し、「ものづくりの背景」を伝える
・NAVICUSと連携してSNS戦略を構築し、多言語での発信を強化
・国内外からの問い合わせが増加し、若い世代や海外顧客の獲得に成功
従来の販路だけでは限界がありましたが、SNS活用によって「伝統工芸×デジタル発信」の可能性を示しました。
京都の伝統産業が世界へ向けて挑戦できることを示す好例です。
京都市×インフルエンサー施策によるインバウンド事例

引用元:PR TIMES
京都市はインバウンド需要を高めるため、インフルエンサーを積極的に活用しています。広告としての一方通行の発信ではなく、体験者のリアルな声を届けることで、旅行者の信頼を得る取り組みです。
HandsUPとの連携によるライブ配信
ECプラットフォーム「HandsUP」と連携し、京友禅や清水焼の職人とインフルエンサーが共演するライブ配信を実施しました。
職人の技を対話形式で紹介することで臨場感を高め、視聴者がコメントで参加できる仕組みを導入したのです。結果として、商品購入や体験予約へと直結する効果を生みました。
韓国市場に向けた現地インフルエンサー活用
韓国の人気インフルエンサーを起用し、現地語で京都の文化や観光地を紹介しました。フォロワーにとっては「信頼できる旅行情報」として受け止められ、訪日意欲の喚起につながった事例です。
これらの施策はいずれも、単なる宣伝ではなく「体験を伴うリアルな声」を届ける点が特徴です。
インフルエンサーを介した発信は、海外ユーザーの共感を得やすく、京都ブランドの国際的な認知を高める有効な手段となっています。
企業がすぐに実践できるSNSアクションプラン

SNSは工夫次第で成果が大きく変わります。企業がまず取り組むべきアクションを紹介します。
1,ターゲット別にプラットフォームを選定する
SNSは利用者層が異なるため、ターゲットに合ったプラットフォームを選ぶことが第一歩です。
・10〜20代:TikTokやInstagram Reelsなど短尺動画に強い媒体
・30〜40代:InstagramやYouTubeで商品の背景やレビューを重視
・ビジネス層:FacebookやX(旧Twitter)が効果的
京都市観光協会がFacebook・Instagram・Weiboなど複数の公式アカウントを運営し、それぞれの特性に合わせた情報発信をしているのは好例です。
自社のターゲットがどこに多いのかを把握し、SNSを選定することが成功の近道となります。
2,短尺動画・長尺動画を組み合わせた運用
短尺動画は拡散力が高く、長尺動画は理解や共感を深めるのに有効です。両者を組み合わせることで、広がりと深みを両立できます。
・短尺動画:冒頭3秒で惹きつける構成、字幕・縦型フォーマットが必須
・長尺動画:商品や体験の背景をじっくり説明し、信頼感を醸成
・活用例:ショート動画で観光スポットを紹介し、詳細はYouTubeで解説
ある調査では「長尺動画を視聴した人の7割以上が購入意欲を高めた」との結果も出ています。目的に応じて動画の長さを使い分けることで、より効果的な発信が可能になります。
SNSアクションプランまとめ

SNS運用は投稿して終わりではありません。データ分析を行い、改善を繰り返す仕組みが成果を左右します。
・投稿時間や曜日による反応率の違いをチェック
・視聴維持率やクリック率を分析し、冒頭や構成を改善
・成功投稿の要素を抽出し、再現性のある運用に反映
京都の観光プロモーションでも、データをもとに動画の長さや投稿頻度を調整し、再現性の高い成果を得ています。SNS運用は投稿して終わりではなく、分析と改善を繰り返すことで成果が積み上がります。
なお、株式会社仕掛人では、YouTube運用をする上でのノウハウをまとめたサイトをご用意しました。
実際に活用できるチェックポイントや改善事例を収録し、すぐに実践できる内容です。京都ブランドを広めたい企業の皆さまは、ご活用ください。
まとめ:京都ブランドをSNSで世界に届けるために

京都ブランドを世界に広めるには、SNSの戦略的な活用が不可欠です。写真に加えて動画で臨場感を伝え、職人の想いや企業の歴史を語ることで共感が生まれます。
多言語対応やインフルエンサーとの連携は、国境を越えて情報を拡散する大きな力となります。実際に観光や伝統産業の事例でも成果が表れており、PDCAを回す継続的な運用が再現性を高めます。
株式会社仕掛人は、エンタメ分野で培った豊富な実績をもとに、企画から分析まで一貫してサポートできる強みがあります。
京都ブランドを「見る観光」から「体験を共有する文化」へと高めたい企業は、まず仕掛人の無料相談をぜひご活用ください。