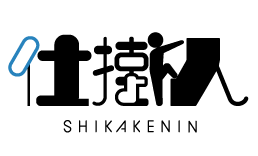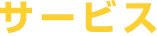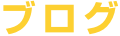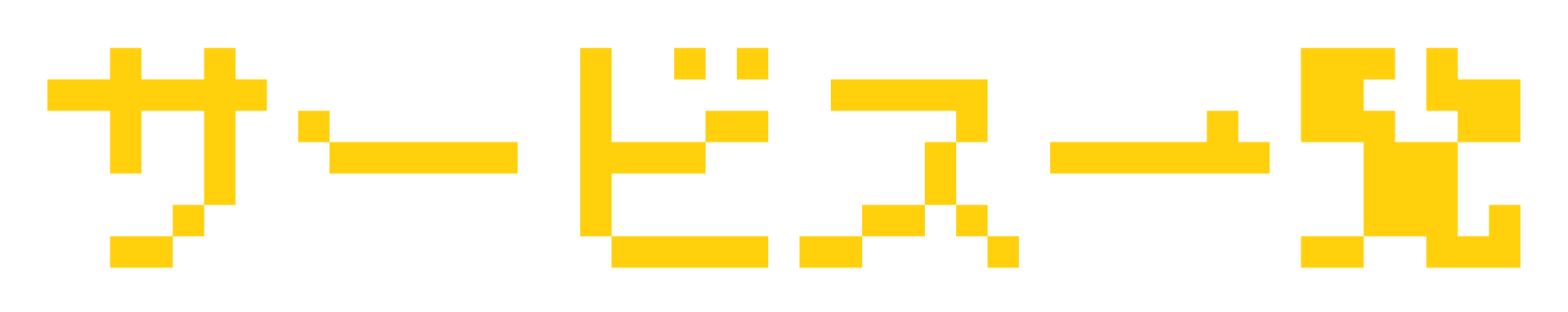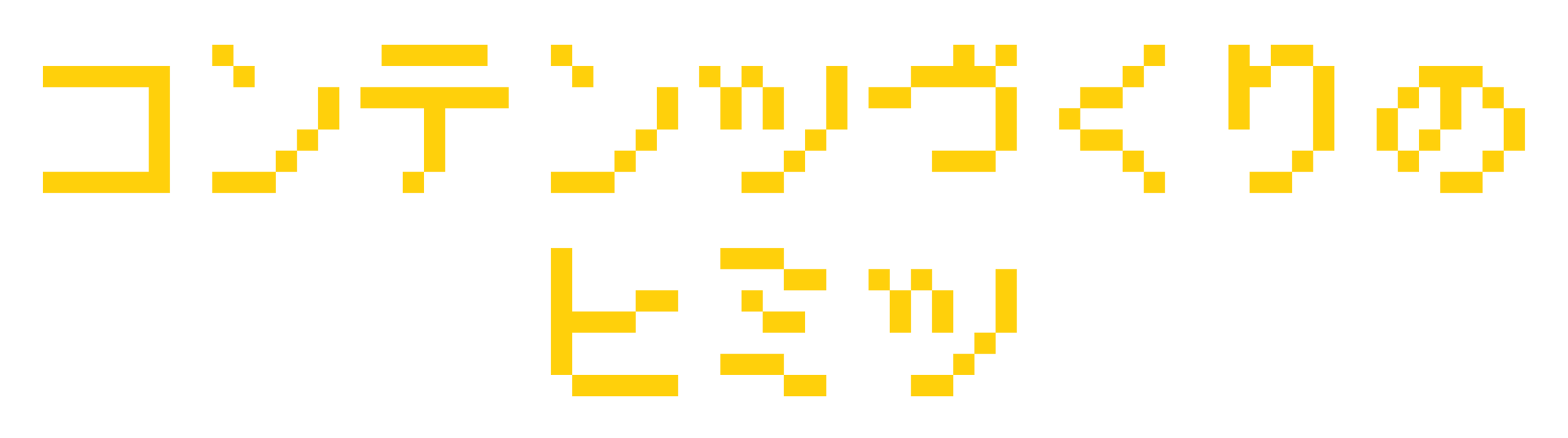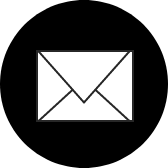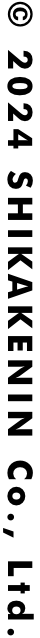京都発、伝統とYouTubeの融合:観光業界が挑む新しい集客戦略
2025.09.16
「パンフレットや広告を出しても観光客が集まらない」
「魅力はあるが代理店にピックアップされていない」
このような悩みを抱える観光産業従事者は少なくありません。旅行者の情報収集源がSNSやYouTube動画へと移り、従来の集客手法が届きにくくなっているからです。
とりわけ、インバウンド需要が高まる今、地域の魅力をどう伝えるかは大きな課題となっています。
京都は、伝統文化を大切にしながらもYouTube動画を活用し、観光プロモーションに新しい道を切り開いています。
本記事では、観光業界に起きている変化や、従来手法の限界を整理し、京都の成功事例を通じてYouTubeを活用した新しい集客戦略を解説します。
もくじ
観光業界の集客に起きている変化

観光業界は大きな転換期を迎えています。旅行者の情報収集源はSNSや動画などへと急速に移行し、従来の媒体だけでは十分に対応できなくなっているのです。
さらに政府のインバウンド施策によって海外需要は拡大を続けることが予想されます。海外からの旅行客であればなおさら、「動画」という情報量の多い媒体は、旅行の不安を和らげ行動を後押しする重要な役割を果たします。
旅行者の情報収集源が大きく変化
観光情報の探し方はこの10年で劇的に変わりました。パンフレットや旅行代理店の案内が中心だった時代から、いまでは InstagramやYouTube動画が主要な情報源になっています。
ある訪日韓国人の調査では、情報収集手段として InstagramとNAVERを使う人が65.5%、YouTubeを使う人が63.9% という高い割合を占めました。Google検索は59.7%で、InstagramやYouTubeが上回る結果となりました。
旅行者は視覚的なコンテンツを通じて、観光地や飲食店の雰囲気を事前に確認しようとしています。この背景には「失敗を避けたい」という心理があります。
動画であれば料理の見た目や施設の雰囲気、人々のリアクションまで把握できるため、文字や写真だけよりも安心して選べるからです。
・SNS・動画が旅行情報の中心に
・従来型レビューサイトは影響力が低下
・動画は体験を事前にシミュレーションできる
今や「旅の第一印象は動画から」という時代に移り変わったといえます。
参照元:2025年 韓国人観光客が情報収集をするSNS・WEBメディアに関する接触調査
インバウンド需要拡大と政府目標
観光は日本経済の成長分野と位置づけられています。政府目標として、2030年までに訪日外国人6,000万人、旅行消費額15兆円 を目指します。
実際の訪日客数は回復傾向にあり、2024年1月から11月までの累計は 3,337万人 に達しました。これはコロナ前の2019年を超える水準です。
ただし外国人観光客の約8割は東京・大阪などの大都市圏に集中し、オーバーツーリズムが大きな課題となっています。
この課題を解決する手段の一つが、地方の魅力を動画で発信することです。温泉や祭り、郷土料理といった独自の資源を映像で見せることで、旅行者の選択肢を都市部から地方へ広げられます。
・政府目標:2030年に6,000万人・15兆円市場
・2024年は3,300万人を突破し回復傾向
・地方誘客のために動画発信が不可欠
参照元:国土交通省
動画が旅行者の不安を取り除く理由
旅行者にとって最大のハードルは「安心して選べるかどうか」です。特に海外から訪れる場合、言語や文化の違いが不安を大きくします。
そこで力を発揮するのが動画です。映像を通じて事前に雰囲気や体験を確認できることで、旅行者は安心して行き先を決められるようになります。
動画が提供できる安心材料には次のようなものがあります。
・宿泊施設や観光地の雰囲気をリアルに確認できる
・食事やアクティビティの様子を事前に把握できる
・コメント欄から他の旅行者の体験談や反応を参考にできる
ある調査では、外国人観光客が日本で最も印象に残った体験は「温泉・ラーメン」でした。
こうした“食”や“体験”は動画によって事前に期待を高めやすく、現地での満足度をさらに押し上げます。
従来の集客方法の限界

観光業界の集客は長らくパンフレットやテレビ広告、旅行代理店に支えられてきました。しかし、情報の鮮度や費用対効果、旅行者の行動の変化を踏まえると、これらの手法だけでは十分な成果を上げにくくなっています。
パンフレットや観光冊子の情報寿命
パンフレットや冊子は写真を多用でき、旅行気分を高める効果があります。現地での持ち歩きにも便利で、案内資料としては一定の役割を果たしてきました。
ただし課題は「情報の寿命が短いこと」です。
・季節のイベントや展示はすぐに更新される
・飲食店や宿泊施設の情報が変わりやすい
・印刷から配布までに時間がかかり最新性を欠く
観光庁の調査でも、旅行者の情報収集はすでにデジタルが中心であり、紙媒体の影響力は縮小しています。パンフレットはあくまで補助的な存在で、来訪を決定づける力は弱まっています。
参照元:観光庁
テレビCMや雑誌広告の費用対効果の低下
テレビCMや雑誌広告はかつて、観光地の認知を一気に広げる有力な手段でした。大規模に発信できる強みはありますが、今では効果が薄れつつあります。
・広告単価が上昇しコスト効率が低下
・消費者の多くがテレビや配信サービスの広告を回避する傾向
・若年層はテレビや雑誌よりSNSやYouTubeを重視
結果として、マスメディア広告は「広く知らせる」には適していても、費用に見合う集客効果を得にくい状況なのです。
旅行代理店任せの集客からの脱却
かつて旅行代理店は、旅行計画から予約までを一手に担う存在でした。しかし現在は、旅行者が自らオンラインで情報を集め、直接予約するスタイルが主流になっています。
これらの数値からも分かる通り、旅行者は「自分で調べ、自分で選ぶ」行動を重視しています。
代理店に依存する集客モデルは縮小し、観光事業者はオンラインを通じて直接旅行者に訴求する力が求められているのです。
YouTubeが観光業界にフィットする理由

YouTubeは映像ならではの没入感、行動に役立つ実用性、共感を生むストーリー性、そして長期的な資産価値を備えています。これらの特徴があるからこそ、観光業界との相性が非常に良いのです。
映像体験が生む没入感と信頼性
動画は「行った気分」を味わえる臨場感を与え、旅行者の不安を取り除きます。写真や文字情報では伝わらない空気感を映像で再現でき、視聴者は現地の様子を事前に体感できます。
さらに、実際の利用者の姿や声が映ることで「ここなら安心」と確信を持てるのです。同時に、「自分もこの体験をしてみたい」という期待を抱かせます。
京都では、街歩き動画や寺社の四季を収めた映像が高い評価を集めています。紅葉に染まる東山の散策や、祇園の街並みを臨場感豊かに伝える映像は、海外視聴者から「まるで自分が歩いているようだ」「静けさと清潔さに驚いた」といったコメントを呼び、実際の来訪意欲を強めています。
・映像は文字や写真では伝わらない空気感を表現
・旅行者にとって“最初の疑似体験”となり目的地選びの決め手に
・京都の街歩きや伝統文化の映像が世界中の視聴者から共感を獲得
・映像は単なる情報ではなく、信頼を築く「体験型のメッセージ」として観光振興に直結
京都の伝統や街並みを映像で届けることは、旅行者に安心感と信頼を与え、観光の新しい入口となっているのです。
アクセスや費用など実用情報の提供
観光動画は感動を与えるだけでなく、旅行計画に役立つ実用的な情報を提供できるのが強みです。
観光庁の調査によれば、訪日外国人が日本出発前に参考にした情報源として「動画投稿サイト」を利用する割合は年々増加し、その他のSNSと並ぶ主要な情報源となっています。
京都では特に、寺社や観光名所へのアクセスや費用感を映像で示すことが有効です。
例えば清水寺までの坂道の様子、嵐山での人力車や竹林散策の料金感覚、祇園エリアでの食事の予算などを動画で伝えると、旅行者は事前に行動をイメージしやすくなります。
・ルートや交通手段を映像で確認できる
・体験や食事にかかる費用感を事前に把握できる
・観光地周辺の雰囲気をリアルに知ることができる
こうした情報は「迷わず行ける」「予想外の出費がない」という安心感につながり、旅行者の不安を和らげます。
YouTubeは単なる宣伝媒体ではなく、旅行計画を支える“シミュレーションツール”として信頼される存在になっているのです。
参考:観光庁
ストーリー性と共感がファンを育てる

観光動画の魅力は、情報だけでなく「物語」を伝えられることにあります。ストーリー性のある映像は視聴者の共感を呼び、ファン化を促します。
京都はその題材が豊富です。町家宿に泊まり、朝の祇園を歩き、夜には京料理を楽しむ。そんな一日の流れを動画にすれば、旅のストーリーが自然と視聴者の心に残ります。
映像を見た人は「自分も同じ体験をしてみたい」と感じやすくなります。
・制作者の体験談や感情を交えた語りは親近感を高める
・Z世代は短尺のストーリー性ある動画を好み、SNSでの拡散につながる
・継続的な発信で「このチャンネルの紹介なら信頼できる」とブランド化が進む
京都の街歩き動画やグルメ紹介では、制作者自身が登場し、食べた感想や街の雰囲気を語ることで多くの共感を集めています。
視聴者はまるで友人から体験談を聞いているように感じ、動画を通じて地域や文化に親しみを持つのです。
ストーリー性のある動画は、観光地を「行きたいと憧れる場所」へと変え、継続的なファンづくりにつながります。
長期的に視聴されるストック型コンテンツ
YouTubeの強みは、一度公開した動画が検索や関連動画を通じて長期的に視聴され続けることです。広告やイベント告知のように短期間で効果が消える媒体とは異なり、観光動画は資産として積み重なります。
京都の観光動画はその典型です。春の桜、夏の祇園祭、秋の紅葉、冬の雪景色、四季折々の映像は毎年繰り返し検索され、シーズンが来るたびに視聴されます。
さらに「京都の寺社めぐり」や「京料理体験」といったテーマは、時期を問わず検索ニーズが高いため、公開から数年経っても再生され続けます。
・季節イベントや四季の景観は毎年需要がある
・寺社や伝統文化は通年で検索されやすい
・動画が積み重なることで資産性が高まり、長期集客を支える
こうして蓄積された動画は、観光地の“デジタル資産”となり、地域全体の知名度と集客力を長期にわたって支えます。
京都のように豊かな季節感や文化を持つ地域では、YouTube活用が特に効果を発揮するのです。
地方観光におけるYouTube活用の可能性

YouTubeは地域の魅力を臨場感ある映像で伝えられるため、観光分散と地域活性化を促す有力な手段となります。
「まだ知られていない地域の魅力」を映像で届け、旅行者の行き先を多様化させる力を持っているのです。
観光協会・自治体の情報発信戦略

引用元:YouTubeチャンネル「青森県知事の新時代ちゃんねる A-Tube」
多くの自治体や観光協会がYouTubeを活用していますが、「動画を作るだけ」で終わり、戦略や仕組みが伴わないケースも少なくありません。観光や地域振興で成果を上げるには、継続的な発信と県民を巻き込む仕組みが欠かせないのです。
青森県はその好例です。職員が撮影した映像をオープンデータ化し、事業者や住民が自由に活用できる体制を整備しました。その結果、さまざまなメディアで動画が使われ、県全体の認知度向上につながっています。
さらに、県知事自ら出演する「青森県知事の新時代ちゃんねる A-Tube」では、県政情報を楽しく分かりやすく発信。
・記者会見やイベントをライブ配信
・「#あおばなオンライン」で県民の質問に直接回答
・ねぶた祭の裏側や菜の花フェスティバルなど文化も紹介
等身大の知事が登場することで親近感が増し、若年層にも届きやすい工夫がされています。短尺動画も取り入れ、「伝わる広報」として定着しつつあります。
自治体が戦略的にYouTubeを運用すれば、観光誘客だけでなく地域ブランド力の強化にも直結するのです。
中小規模の宿泊・飲食事業者の成功余地

引用元:石見神楽ライブ配信
YouTubeは自治体だけでなく、中小規模の事業者にとっても有効なツールです。コロナ禍で直接見られなくても、島根県の石見神楽ではライブ配信が観光客の関心を集め、地域への注目度を高めました。
また、「ウサギ島」「スノーモンキー」など地方ならではのユニークな体験は、動画をきっかけに国内外で拡散し、訪問動機の創出につながっています。
・ライブ配信や短編動画でも成果を出せる
・独自の文化や自然が動画で話題化しやすい
・大きな予算がなくても「リアルな映像」が旅行者を動かす
YouTubeは、都市部に集中する観光需要を地方に分散させ、地域経済を支える強力な手段です。自治体は戦略的に発信を行い、中小事業者は独自の魅力を動画で伝えます。
これにより、埋もれていた地域資源を「行きたい理由」へと変えられます。映像発信は、地方創生の新しい起爆剤となるのです。
効果的なYouTube活用のポイント

YouTubeを観光業界で成果につなげるには、戦略的な設計が欠かせません。
重要なポイント
1.ターゲット設定
2.映像と情報の両立
3.視聴者との交流
4.継続的な発信
1.ターゲット設定とコンテンツ企画
動画の企画でまず意識すべきは「誰に届けるのか」という明確なターゲット像です。視聴者像が決まれば、言語、映像構成、紹介する内容も自然に定まります。
・外国人旅行者向け → 英語字幕や交通案内を加える
・Z世代向け → ショート動画やテンポの速い街歩き企画
・ファミリー向け → 子どもと楽しめる体験や施設紹介
ターゲットに合わせてテーマを設計することで、「自分のための情報だ」と視聴者に感じてもらえ、視聴完了率や拡散率が高まります。
2.映像美と情報の両立
観光動画では、美しい映像が関心を引き、実用情報が行動を促します。どちらかに偏ると効果は半減します。
・高画質映像やドローンで臨場感を演出
・テロップでアクセスや料金などの実用情報を補足
・景観と情報を組み合わせて「見たい」から「行きたい」へつなぐ
たとえば長崎や栃木のPR動画では、絶景映像に具体的な体験情報を加え、「訪問の後押し」に成功した事例です。
参照元:長崎県観光連盟公式チャンネル・「15Tube〜栃木県公式〜」
3.インタラクションの活用
YouTubeは一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションが可能です。視聴者を巻き込む仕組みがファン化を促します。
・コメント欄で質問に答える
・視聴者アンケートで次回の企画を決定
・ライブ配信で現地と視聴者をリアルタイムにつなぐ
交流が深まることで「自分も参加している」という感覚が生まれ、単なる視聴者からファンへと変わっていきます。
4.継続的なシリーズ化と世界観の統一
動画は単発で終わらせず、テーマをシリーズ化して発信を続けることが大切です。定期更新が視聴習慣を育て、チャンネルのブランド化につながります。
・季節の旅やご当地グルメをシリーズ化
・サムネイルやBGMを統一し、世界観を確立
・蓄積した動画が資産となり、長期的な集客を支える
継続性と一貫性は「このチャンネルなら信頼できる」という認識を強め、観光地全体のブランド価値を高めます。
こうした取り組みを着実に進めるには、専門家の知見を取り入れるのが近道です。
京都発のYouTube支援企業「仕掛人」では、戦略立案から制作・分析まで一括支援を提供しており、無料相談も可能です。
まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。
京都から学ぶYouTube成功事例

京都では、街歩き動画やグルメ特化チャンネル、イベント映像の活用など、YouTubeを通じた多彩な取り組みが観光誘客につながっています。
映像は旅行者に没入感と安心感を与え、実際の来訪を後押しします。
街歩き動画が生む没入感

京都郊外散策ツアー – 日本の郊外を探索【4K HDR – 60fps】
このような街歩き動画は、視聴者に“実際に歩いている感覚”を提供します。
・海外視聴者から「別の惑星にいるよう」「日本の清潔さに感動」といったコメント
・映像を通じて街の静けさや生活感がリアルに伝わる
・ガイドブックでは得られない「音」「雰囲気」「空気感」を体験できる
効果として、没入感が「実際に行ってみたい」という旅行意欲を強く刺激します。
グルメ特化チャンネルの集客力

引用元:ロジウラTV 京都&全国グルメ
ロジウラTV 京都&全国グルメ
京都の人気グルメ情報を長年の食べ歩き経験から厳選して紹介しています。
・月間60万アクセスを誇る「京都速報」と連動
・実際の料理や店内の雰囲気を動画で確認可能
・全国のグルメも扱い、幅広い層の関心を獲得
効果として、「食」を軸にした動画は観光の大きな動機となり、来訪や再訪を後押しします。
動画を見て「行きたくなる」心理効果

引用元:【公式】京都水族館
京都水族館の「夜のすいぞくかん」
イベント専用のオリジナルムービーを制作しています。夜の生き物の姿や幻想的な雰囲気を映像で伝えました。
・映像で昼間とは異なる魅力を演出
・来館前から「特別な体験ができる」という期待感を醸成
・参加者がイベントをより深く楽しめるようサポート
効果として、体験を事前に疑似体験できることで「自分も参加したい」という心理を引き出します。
このように、京都の成功事例からわかるのは、YouTubeが情報発信を超えて「体験の入口」になるということです。
・街歩き → 没入感で観光意欲を喚起
・グルメ紹介 → 信頼感ある食体験で集客
・イベント映像 → 期待感を高め来館を促進
映像は旅行者の不安を解消し、具体的な行動につながる力を持っています。観光地はYouTubeを通じて「行きたくなる理由」を創り出せるのです。
まとめ:伝統とYouTubeがつなぐ新しい観光戦略

観光業界は従来の集客手法だけでは成果を上げにくくなり、YouTubeの活用が不可欠となっています。
旅行者は動画を通じて体験を疑似的に味わい、安心感や期待感を得ることで「行きたい」という行動につながります。
京都の事例が示すように、街歩き映像の没入感、グルメ動画の信頼性、イベント映像の特別感は、地域の魅力を新しい形で発信する有効な手段です。
今後は自治体や事業者が戦略的に動画を継続活用し、地域ブランドを育てることが重要です。その一歩を踏み出すなら、京都発のYouTube支援企業「仕掛人」の無料相談がおすすめです。
観光資源を“行きたくなる理由”へと、磨き上げる確かな力を提供しています。
まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。