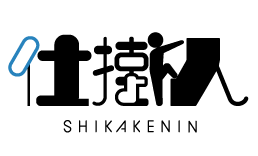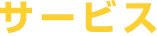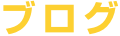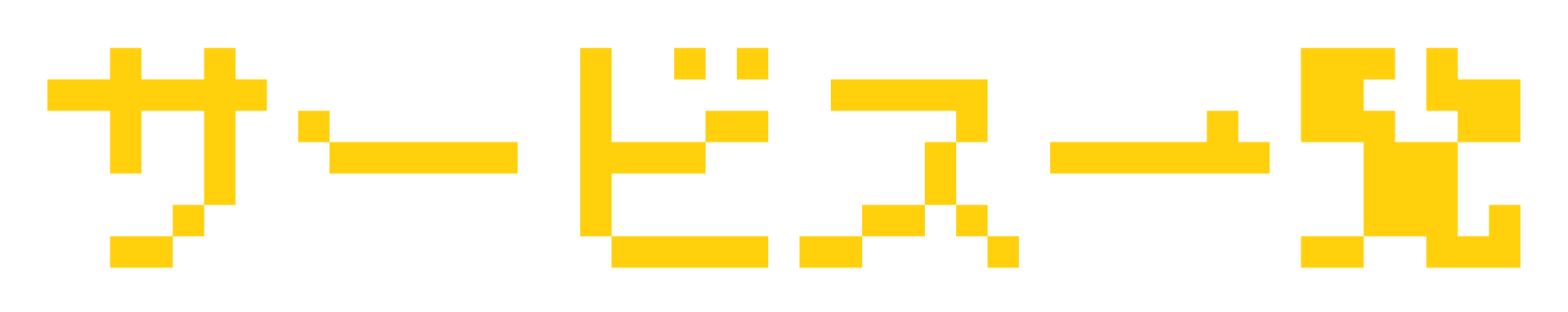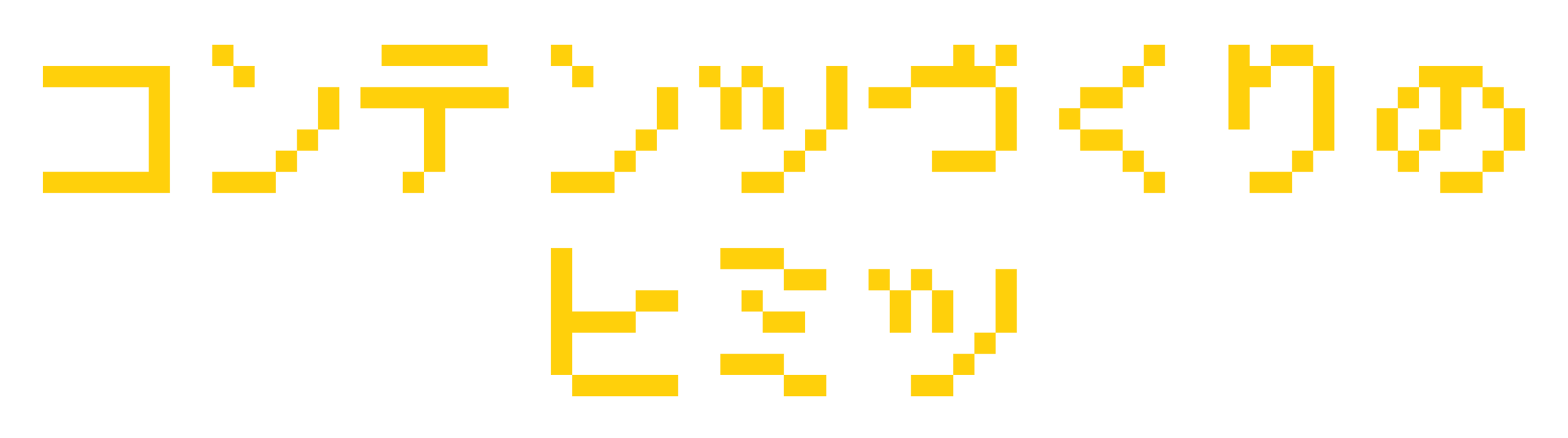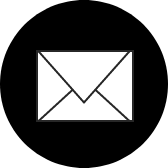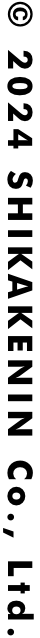【企業PRの新定番】YouTubeショートとTikTok比較ガイド
2025.08.19

企業のPRの場として、TikTok、YouTubeショートやInstagramリールなど、短時間で印象を残せるショート動画が注目を集めています。
しかし、ただ投稿を続けるだけでは効果は得られません。明確なターゲット設定や企画力、拡散設計を欠けば、再生数もブランド浸透も思うように伸びないのです。
本記事では、企業PRにおけるYouTubeショートとTikTokの特性を比較しました。また、成果につながる活用ポイントと成功事例もご紹介します。自社に最適なPR戦略が描けて、動画施策を確実に加速できるでしょう。
もくじ
ショート動画が企業PRの新定番になった理由

スマホ利用の普及とSNS動画視聴の定着により、ショート動画は日常生活の一部となりました。短時間で魅力を伝えられる特性は企業PRと好相性なのです。
採用広報・販売促進・ブランド発信など幅広い目的で活用が急速に広がっています。
ショート動画市場の拡大と企業活用の増加
動画広告市場は、ここ数年で急成長を遂げています。
・インターネット広告費:3兆6,517億円(前年比106.5%)
・動画広告費:1兆7,383億円(前年比110.9%)
市場成長の背景には、利用者の視聴習慣の変化があります。
総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、SNSの利用率は80.8%、無料動画共有サービスの利用率は62.7%と高水準を維持しています。
スマホ保有率も78.9%に達しました。20〜50代は約9割が所有し、いつでもどこでも動画を視聴できる環境が整いました。市場拡大の土台になっています。
このような環境を追い風に、企業の活用も急速に広がり、ショート動画の導入が以下のように進んでいます。
| 活用目的 | 主な内容 | 具体例 |
| 採用広報 | 社員の日常や職場紹介 | 社員密着動画 |
| 商品PR | 新製品紹介・使い方説明 | 使用感レビュー |
| 観光・自治体PR | イベント告知や観光スポット紹介 | 縦型観光CM |
採用現場から地域振興まで幅広く使われ、企業規模や業種を問わず導入事例が増加しています。SNSでの拡散性が高いショート動画は、広告投資効果の面で魅力的な手法なのです。
参照元:総務省「令和5年通信利用動向調査」
電通「日本の広告費 2024」
なぜ今、企業PRにショート動画が必要なのか
ショート動画が求められる背景には、現代の情報消費スタイルの変化が挙げられます。スマートフォンの縦型全画面表示は没入感が高く、わずか数十秒〜1分程度でも十分な情報量を伝えられます。
Z世代やミレニアル世代は短尺コンテンツの消費が主流で、長尺動画よりも短い動画に高いエンゲージメントを示しています。
さらに、YouTubeショートやTikTokといったプラットフォームは、フォロワー数に依存しないレコメンド型アルゴリズムを採用しています。
ユーザーの視聴履歴や行動データをもとに、興味・関心に合った動画を自動表示する仕組みです。
これにより、既存ファンだけでなく新規顧客や潜在層にも自然にリーチでき、広告配信とオーガニック投稿の双方で高い拡散効果を期待できます。
制作面でも、ショート動画は低コスト・短納期で作れる点が企業にとって魅力です。トレンドやキャンペーンに素早く対応し、試作→配信→改善のサイクルを高速で回せます。
企業PRでの活用は、以下のような分野で特に効果を発揮します。
| 分野 | メリット | 具体例 |
| 採用 | 人柄や社風を直感的に伝える | 社員出演の企画 |
| ブランド強化 | ストーリーや理念を短尺で表現 | ブランドムービー |
| 販売促進 | 商品の魅力を瞬時に訴求 | 使用シーン動画 |
こうした特性は、単なる情報発信を超えて企業の価値を感覚的に理解させる役割を果たします。
市場の拡大とユーザー行動の変化を踏まえると、ショート動画は今後ますます企業PRの主力手法として定着していくと考えられます。
YouTubeショートとTikTokの基本

縦型・短尺のショート動画は、今やSNSの主役です。
中でもYouTubeショートとTikTokは企業PRに欠かせない存在になっています。その仕組みや特徴を理解し、自社に最適な活用方法を見極めましょう。
YouTubeショートとは?
YouTubeショートは、YouTubeが提供する縦型・短尺動画の投稿機能です。最大3分まで対応し、スマートフォンから手軽に撮影・編集・公開できます。縦型9:16の全画面表示で、視聴者の没入感を高める設計が特徴です。
・作成方法
YouTubeアプリ内「ショートカメラ」で撮影、または既存動画を3分以内に編集
・編集機能
速度調整・テキスト挿入・複数クリップ結合・フィルターなど
・拡散経路
YouTubeショートフィードや関連動画で新規視聴者に表示
・収益化
パートナープログラム参加者は、ショート動画の再生から広告収益分配が可能
既存の長尺動画やライブ配信と連動できるため、チャンネル全体の視聴時間や登録者増加につながりやすいです。
TikTokとは?
TikTokは、ByteDance社が提供するショート動画プラットフォームです。アプリ内での撮影は最大3分、アップロードは最大で10分対応可能です。
音楽やエフェクトを使ったクリエイティブ表現に強みがあります。
・撮影・編集
音楽ライブラリ・テンプレート・エフェクト・テキスト・速度調整など多彩
・画面仕様
縦型9:16推奨でスマホ視聴に最適化
・拡散経路
「For You」フィードによるレコメンド配信で、新規視聴者へのリーチが容易
・収益化
条件を満たせば「クリエイター報酬プログラム」やブランド案件で収益化可能
フォロワー数に依存しないアルゴリズム設計により、新規顧客層や潜在層への接触に優れています。
トレンド適応が速く、企業はこの特性を活かして話題性の高いプロモーションや採用動画を配信しています。
企業PRにおけるメリット・デメリット

ショート動画は拡散性と訴求力を兼ね備えた有力なPR手法です。けれど、プラットフォームごとに特性が異なります。
YouTubeショートとTikTok、それぞれの強みと注意点、さらに二刀流運用の可能性と課題を解説します。
YouTubeショートの場合
YouTubeショートは、長期的な集客とブランド構築に適したプラットフォームです。動画はYouTube内の検索結果や関連動画に表示され続けます。公開後も安定して視聴されやすく、資産型コンテンツとして機能します。
また、既存のロング動画やライブ配信と連動させることで、視聴時間やチャンネル登録者数を伸ばす施策が組みやすいのも特徴です。
メリット
・長期的な再生獲得(ストック型)
・幅広い年齢層へのリーチ(10〜40代以上)
・既存チャンネルとの連動で相乗効果
・広告収益化制度が整備済み
注意点
・競合が多く、視聴維持率やクリック率が低いと露出が減少
・拡散スピードはTikTokより遅く、即効性に欠ける場合がある
TikTokの場合
TikTokは即効性のある拡散力とトレンド適応の速さが魅力です。
レコメンド型の「For You」フィードはフォロワー数に依存せず、新規層にも動画を届けやすいため、ゼロからでも大きなバズを狙えます。
また、音楽やエフェクトなどの編集機能が豊富です。スマホだけで完結できる制作環境は企業にとっても参入しやすい要因になってます。
メリット
・フォロワーゼロからでも拡散可能
・トレンドに素早く乗れる
・制作コストが低い
・10〜20代への高い到達率
注意点
・動画寿命が短い傾向にあり、継続露出には高頻度投稿が必要
・企業の広告色が強すぎるとエンゲージメントが低下
・ブランドトーンの維持が難しい場合あり
二刀流運用の可能性と制約
YouTubeショートとTikTokを併用する「二刀流運用」は、両者の特性を活かしてPR効果を最大化できます。
例えば、TikTokでトレンドを活用して短期的に注目を集め、そのコンテンツをYouTubeショートに展開して長期的な視聴を獲得する流れです。
新規層と既存層の双方をカバーできます。
可能性
・トレンド拡散と長期視聴の相互補完
・ターゲット層の幅広いカバー
・動画素材の二次利用で制作効率化
制約
・媒体ごとの編集最適化が必須(冒頭演出・テロップ位置・BGMルールなど)
・運用管理の負荷増大
・成果時期のズレ(TikTok=即効型、YouTubeショート=蓄積型)
ショート動画は、拡散力と持続性を兼ね備えた企業PRの強力な武器です。特性を理解し、自社に合った運用を選びましょう。
短期間で注目を集め、長期的な成果へとつなげられます。
YouTubeショートとTikTokの違い
同じショート動画でも、YouTubeショートとTikTokは大きな違いがあります。それぞれの特性を把握することで、自社PRに適した運用戦略が描けるでしょう。
以下、2つのポイントを比較します。
① ユーザー層の違い
② 動画時間と拡張性
① ユーザー層の違い
YouTubeショート
YouTube全体の利用者層を反映し、10〜50代以上 まで幅広く利用されています。特に30〜40代の比率がTikTokより高く、BtoB商材や高価格帯サービスの訴求にも対応しやすいです。
世界で月間ログインユーザー20億人以上という巨大な基盤を持つため、幅広い層に継続的なリーチが可能です。
TikTok
10〜20代前半が中心で、Z世代の利用率が突出しています。音楽・エンタメ・ファッションなどトレンドに敏感な層が多く、ブランドや商品の話題化に向いています。
近年は30代以上の利用者も増加中で、ファミリー層や趣味領域の動画も伸びています。
| プラットフォーム | 主な年齢層 | 特徴 |
| YouTubeショート | 10〜50代以上 | ・幅広くリーチ可能 ・長期視聴に強い |
| TikTok | 10〜20代中心 | ・トレンド消費 ・若年層拡散に強い |
② 動画時間と拡張性
YouTubeショート
2024年以降、最大3分の運用が始まりました。
既存の長尺動画やライブ配信と連動できるため、チャンネル全体の視聴時間や登録者増加にもつながります。
コンテンツ資産化が可能で、公開後も検索や関連動画から視聴され続けるのが強みです。
TikTok
アプリ内撮影で最大3分、端末からのアップロードで最大10分までの長尺投稿も可能です。
尺の自由度は高いものの、ユーザーの視聴習慣としては短尺コンテンツが主流で、数十秒でインパクトを与える構成が求められます。
| プラットフォーム | 最大動画時間 | 特徴 |
| YouTubeショート | 3分 |
・長尺との連動 ・資産型運用 |
| TikTok | 10分 | ・柔軟な尺設定 ・即効性重視 |
企業PRの成功事例

企業PRでは、動画を通じて企業の雰囲気や人柄を伝えることで、共感や信頼を得やすくなります。
以下、TikTokとYouTubeショート、それぞれの特性を活かして話題化とブランド価値向上に成功した事例を紹介します。
【TikTok】三和交通:「踊るおじさん」で親近感とバズを獲得

引用元:三和交通公式ページ
神奈川県のタクシー会社・三和交通は、TikTokで社員や役員が制服姿のまま人気楽曲に合わせて踊る「踊るおじさん」シリーズを配信しています。
堅い業界イメージとのギャップが話題となりました。動画によっては数十万〜数百万回の再生を記録しています。
採用広報としても効果を発揮し、「働いてみたい」という声が多く寄せられました。
・トレンド曲・人気エフェクトを活用し、拡散力を強化
・社員出演で企業文化や人柄を自然に表現
・広告感を抑え、親しみやすさを前面に出した演出
・再生数数十万〜数百万回を達成し、応募意欲を喚起
企業の堅い印象を柔らかく変え、応募意欲を高める好例です。遊び心と戦略性を兼ね備えた企画は、採用ブランディングに直結します。
【YouTubeショート】株式会社わかさ生活:キャラクターを活かした多様な企画

引用元:株式会社わかさ生活公式ページ
健康食品メーカーのわかさ生活は、自社マスコット「ブルブルくん」を主役にしたYouTubeショートを多数展開しています。
クイズ・豆知識・社員の日常など企画が多彩で、またそれぞれに統一感があることで、ブランドの世界観を視聴者に浸透させています。既存顧客のロイヤリティ向上に加え、新規層にも親しみやすく商品認知を広げています。
・キャラクターを軸にエンタメ性と情報性を両立
・短尺動画で完結しつつ長尺動画やキャンペーンサイトに誘導
・社員のキャラ付けがしっかりしていて、次の企画も楽しみになる
キャラクターを核に世界観を築き、短尺でもブランド価値を的確に伝える好例です。商品認知とファン化を同時に進められます。
成果を出すためのポイント

運用において成果を上げるには、ターゲット設定・企画設計・データ分析まで、一貫した戦略を組み立てることが欠かせません。
各要素の精度を高め、相互に補完し合う形で継続運用し、成果を最大化できます。
ターゲットとペルソナを明確に設定
動画制作の出発点は、明確なターゲット像と詳細なペルソナ設定です。
・年齢
・性別
・地域
・興味関心
・視聴する動機
・日常的な行動特性
これらを掘り下げて特定します。
これにより、ターゲットの心に響く企画や訴求ポイントを明確にできます。
競合チャンネルの人気動画やコメント傾向を分析し、視聴者が求めるテーマやトーンを把握することが効果的です。これにより、動画の方向性がぶれず、響く内容が作れます。
・年齢・性別・興味・悩みを具体化
・視聴動機と動画目的の一致
・競合分析で好まれる構成・尺を把握
明確なターゲット設定は動画の軸になります。ペルソナを細かく描くほど、視聴者が「自分のための動画」と感じやすくなります。
冒頭3秒で惹きつける企画設計
ショート動画は冒頭3秒が勝負です。
最初の一瞬で興味を持たせる演出を取り入れることで、視聴維持率が大きく向上します。数字や質問で始める、動きのある映像を入れる、音や効果でインパクトを出すなど、スクロールを止める工夫が必要です。
・冒頭に結論やベネフィット、続きが気になる「前フリ」を提示
・動きや音で変化を与える演出
視聴者の指を止めるための3秒は、動画全体の命綱です。開始直後の掴みが弱いと、その先は見てもらえません。
継続運用とデータ分析による改善サイクル
短期的なバズだけでは成果は持続しません。
週2〜3本の安定した投稿を継続し、アナリティクスで視聴維持率・視聴者層などを分析します。
高パフォーマンス動画の要素を抽出し、次の企画や編集に反映させます。データに基づく改善を繰り返し、視聴者層の拡大と再生数の安定が可能です。
・投稿ペースを固定し習慣化
・アナリティクスで成果要因を特定
・改善点を次の動画に反映
継続と改善の積み重ねが、チャンネル成長の本質です。データを無視した運用は、長期的には伸び悩みます。
まとめ – 自社に最適なPR戦略で成果を最大化

ショート動画は、短い時間で強い印象を残せる現代のPRに欠かせない手法です。しかし、ただ配信するだけでは効果は限定的になります。
明確なターゲット設定・興味を引く企画・継続的な運用と改善が揃って、真の成果が生まれます。
これらを体系的に実践すれば、短期間で認知を拡大させ、長期的にブランド価値を高められます。
なお、株式会社仕掛人は、戦略立案から動画制作・配信・効果検証まで一貫してサポートします。企業が自力では難しい「短期間で伸ばし、長期間成果を出す」道筋を描きます。
PR施策を一歩先へ進めたい企業は、自社に最適化されたYouTube戦略を導入してみてください。
まずはお気軽にご相談ください。