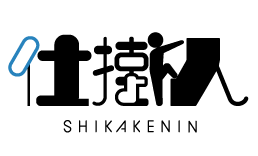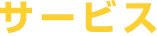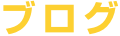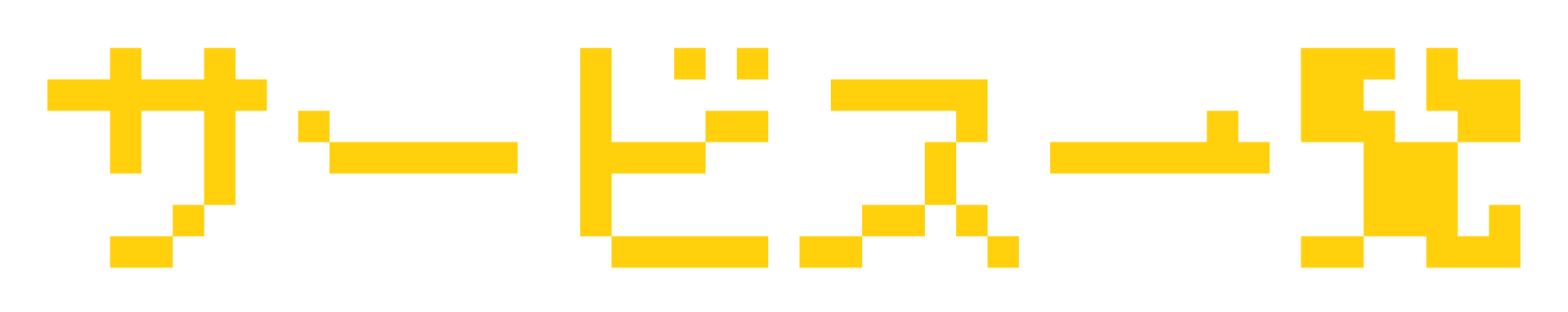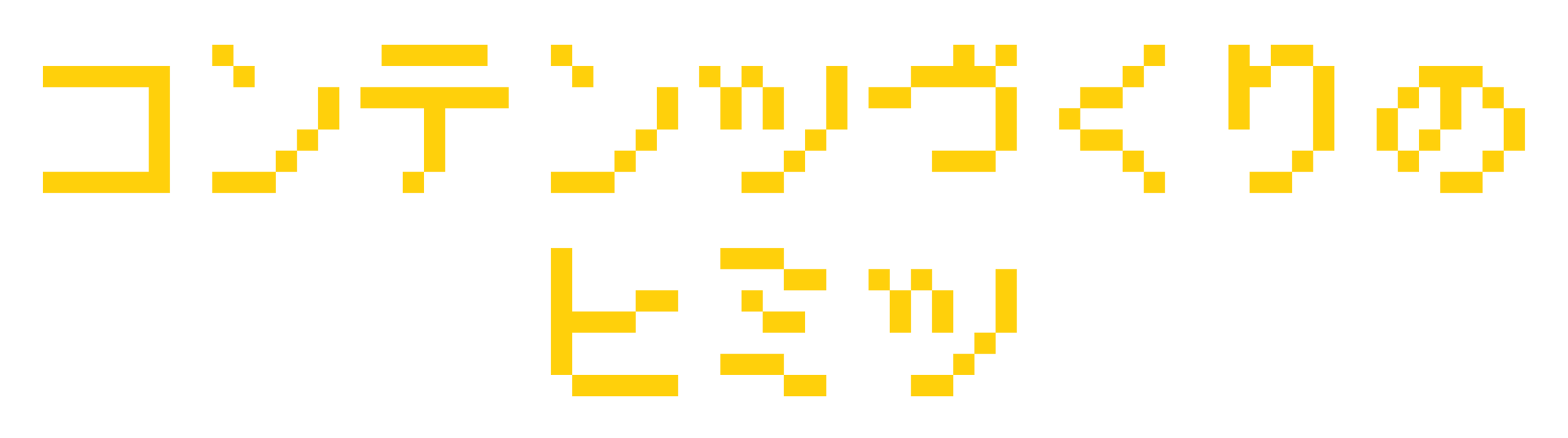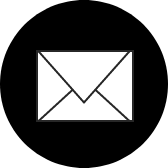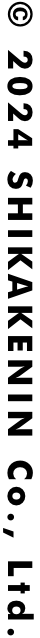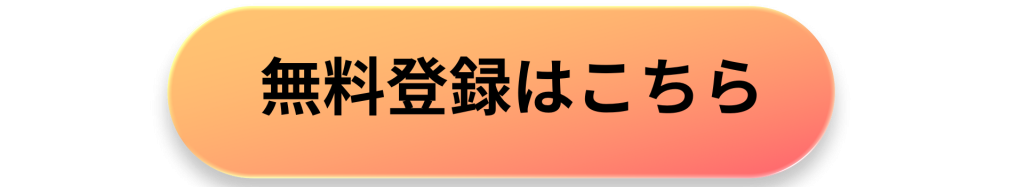“売る動画”ではなく“愛される動画”:企業がブランドを築く動画戦略
2025.09.09

「動画を活用しても再生されない」
「宣伝っぽくて敬遠されてしまう」
このような悩みを抱える企業は少なくありません。商品を紹介するだけでは視聴者の心をつかめず、むしろ逆効果になることもあるのです。
今の時代に求められるのは、売り込むのではなく「愛される動画」です。視聴者に共感や学び、楽しさを届けることで、ブランドは自然に信頼され、ファンが育っていきます。
本記事では、愛される動画がなぜ強いブランドを築くのか、その理由と具体的な実践方法を事例とともに解説します。
もくじ
「愛される動画」が企業ブランドを築く理由

企業が動画を活用する際に重要なのは、商品を売り込むことではなく、ユーザーの心を動かす動画を届けることです。
従来の広告型コンテンツは敬遠されがちですが、共感や学び、驚きを与える動画は拡散され、自然と口コミやファン形成へとつながって行きます。
広告動画が見られなくなった背景
YouTubeやTikTokの人気コンテンツを見ても分かるように、動画は「情報収集」ではなく「娯楽」や「暇つぶし」として消費される傾向にあります。そのため、一方的に商品説明や宣伝を行うだけの広告動画は視聴されにくいです。
たとえば次のような動画は再生維持率が低くなりがちです。
・企業紹介や商品機能の説明だけに終始する動画
・専門用語が多く一般視聴者が置き去りになる解説
・宣伝色が強すぎて“押し売り感”が漂う映像
視聴者は広告を避ける一方で、物語性や体験を盛り込んだ動画に関心を示します。製品紹介であっても、ストーリー仕立てにすれば「広告」ではなく「エンタメ」として受け入れられるのです。
視聴者が求めるのは「共感・学び・驚き」
短尺の動画は数十秒で感情を動かす力を持ちます。
視聴者が期待しているのは、自分ごととして感じられる共感や、日常で役立つ知識、そして予想を裏切る驚きです。
具体的に求められる要素は以下の通りです。
・共感:自分の体験と重ね合わせられるストーリーや人物像
・学び:専門性をかみ砕いて提供される豆知識やノウハウ
・驚き:意外性のある展開や視聴者の予想を裏切る演出
ある飲料ブランドは、復興支援活動をテーマにZ世代向けのショート動画を制作しました。単なる商品紹介ではなく、若者が現地を訪ねるロードムービー風の構成です。
「飲んでみたい」「応援したい」という共感が広がって、商品だけでなく活動そのものに対する支持を集めることに成功しました。
「愛される動画」が口コミとファン形成を生む
動画は一度きりの接触で終わるのではなく、コメントやSNSでの共有を通じて広がっていきます。とくにショート動画では「みんなのコンテンツ」として扱われやすく、視聴者が自発的に関与する流れが起きやすいのが特徴です。
・コメント欄で「自分も試した」「買ってみた」と共感の声が集まる
・ハッシュタグや検証動画が連鎖的に広まり、二次的な発信者が増える
・継続的な発信によって「最近よく見るブランド」として認知される
生活用品の事例では、TikTok上で一般ユーザーが「検証動画」を多数投稿し、それが購買行動につながりました。こうした現象は、企業発の広告を超えて、ユーザー同士の口コミに支えられたファン形成へと発展します。
広告予算に依存するのではなく、ユーザーの参加や共感を呼び込む仕組みを作ることが、長期的に愛されるブランドを築く道筋となります。
企業動画の目的と役割を整理する

企業が動画を制作する目的は一つではなく、主な目的は以下の4つが挙げられます。
1,ブランドの世界観を浸透させる
2,新しい顧客層へ広げる
3,購買行動を後押しする
4,社員やファンとのつながりを深める
こうした多面的な役割を果たすのが企業動画の目的です。
1.ブランディング強化としての動画活用
動画は、ブランドの理念や価値観を「視覚と聴覚」で直感的に伝えられる媒体です。文字や写真では表現しきれない「空気感」や「質感」まで届け、視聴者の感情に訴える力があります。
北欧、暮らしの道具店

引用元:北欧、暮らしの道具店
暮らしに役立つ知恵や雑貨・インテリアの紹介を丁寧に行うことで、視聴者の日常に寄り添う温かみのあるコンテンツを発信しています。
「自分もこんな暮らしをしてみたい」といった共感の声が多く寄せられ、ブランドに対する憧れや好感度を高めています。
ブランド動画制作のポイント
・世界観の一貫性
配色・BGM・編集のトーンを揃え、動画全体でブランドの統一感を示す
・理念やストーリーの可視化
単なる商品の説明ではなく、ブランドが大切にする価値観や暮らしの哲学を物語として描く
・感情を動かす訴求
機能や価格ではなく「その商品でどんな体験ができるか」「どんな気持ちになれるか」を伝える
・視聴者の共感を得る工夫
暮らしの悩みや憧れに寄り添い、「自分ごと」として感じてもらえるテーマを取り上げる
このように、「北欧、暮らしの道具店」のチャンネルはブランドの世界観を体験として届けることで、多くの共感と支持を獲得しています。
動画はブランドを“好きになってもらう”最短の手段であることを示す好例といえるでしょう。
2.認知拡大・新規顧客の獲得

動画は拡散力が高く、これまで接点がなかった層にもブランドを自然に届けることができます。YouTubeの「おすすめ表示」やSNSのアルゴリズムを活用すれば、短期間で認知度を高められるのも強みです。
いばキラTV(IBAKIRA TV)

茨城県の公式チャンネルでありながら、親しみやすいコンテンツで若年層から幅広い支持を得ています。特にご当地Vtuber「茨ひより」を活用した動画は、硬い行政情報をやわらかく伝える工夫が施され、地域への関心を持たせるきっかけになっています。
自治体発のチャンネルでありながら「楽しく見られる」という点が大きく評価され、観光・移住施策の認知拡大にもつながっているのです。
効果的に認知を広げるための工夫
・難しい説明はキャラクターや映像表現に置き換える
行政や商品情報など硬い内容でも自然に理解されやすい。
・短尺で気軽に見られる動画設計
1〜3分で終わる構成にしてSNSでシェアされやすくする
・共感・話題性のある要素を盛り込む
Vtuberやご当地ネタを取り入れ思わずシェアしたくなる工夫をする
動画は文字や写真では伝わりにくい空気感を表現でき、人々の記憶に残ります。いばキラTVのように、情報をエンタメ化して届けることで「これまで届かなかった層」への認知を広げることが可能です。
3.購買行動を促す導線設計
動画は「買うか迷っている」顧客に最後の一押しをする力を持っています。ランディングページやECサイトに埋め込むことで、理解を深めながら購買へと導けるのが大きな強みです。
GoPro Tips

引用元:GoPro Tips
新製品の機能紹介や撮影テクニックをわかりやすく解説しています。旅行や日常のシーンをGoProでどう撮れるのかを具体的にイメージさせてくれます。
視聴者は「自分もこの映像を撮ってみたい」と感じ、購入やアクセサリーの追加検討につながるのです。製品の利用シーンをリアルに見せることで、購買意欲を高める導線が構築されているのです。
購買導線を設計する際のポイント
・How to型の使用シーンを見せる
製品を使う場面を具体的に描き、利用イメージを持たせる
・動画内でCTA(行動喚起)を明示する
動画内テキストや概要欄で購入ページや関連商品へ誘導する
・導入後の未来像をストーリー化する
「このカメラで旅行を撮ればこんな体験が残せる」と未来を映像で提示する
商品動画は、視聴者に「自分も使ってみたい」という気持ちを生み出す強い力を持っています。GoPro Tipsのように、活用シーンとメリットをリアルに伝えることで、購買へつながる一押しとなり、導線設計として欠かせない存在です。
4.社員・ファンとのエンゲージメント向上
動画は外部顧客だけでなく、社内や既存ファンとの関係強化にも役立ちます。社員のモチベーションを高めたり、ファンの共感を育んだりする“つながりの道具”としても重要です。

引用元:サントリー公式チャンネル
サントリーはYouTubeを活用し、消費者・社員・ファンの3つの接点を意識した動画マーケティングを展開しています。
工場見学や製造現場の様子を公開するだけでなく、実際に働く社員のインタビューを交え「安心・安全な商品づくり」へのこだわりを発信しました。
これにより消費者にはブランドへの信頼感を、社員には自分の仕事が社会に伝わる誇りを生み出し、双方のエンゲージメントを高めています。
エンゲージメントを高める動画の形
・社内向け:オンボーディング動画・代表メッセージ・イベント記録
・ファン向け:舞台裏映像・インタビュー・双方向配信(ライブ配信など)
特にライブ配信のようにコメントを通じて視聴者が参加できる形式は、単なる視聴から「共創体験」へと変わり、長期的なファン化に直結します。
このように、企業動画は、主に4つの役割を持ちます。それぞれに最適な設計が求められているのです。
参照元:ムーバル「動画制作は目的を明確にすることが1番大事!」
企画段階で抑えるべきポイント

動画の成果は、企画の段階でどれだけ土台を作れるかによって大きく変わります。
1,ターゲットを具体的に描く
2,チャンネル全体の方向性を統一
3,繰り返し使える型を設計する
4,サムネイルやタイトルを磨く
これらを整えることで、安定して成果を積み上げる運営が可能になるので、それぞれのポイントを解説します。
1.ペルソナ設定とニーズリサーチ
動画制作の第一歩は「誰に届けるのか」を明確にすることです。属性だけでなく、視聴者が抱える悩みや、動画から得たい体験まで掘り下げる必要があります。
たとえば「20代社会人男性」という枠だけでは不十分です。
「仕事が忙しく料理の時間を短縮したい」「楽しく学びながらスキルを身につけたい」といった具体的なニーズまで言語化すると、企画の方向性が定まります。
・基本属性:年齢・性別・職業・居住地など
・ライフスタイル:日常の過ごし方・休日の行動パターン
・視聴動機:暇つぶし・学習・娯楽・自己投資など
・抱える悩み:時間がない・知識不足・情報が複雑すぎるなど
・動画で得たい価値:共感したい・笑いたい・学びたい・課題を解決したい
こうした設計を行うことで、視聴者は「これは自分のための動画だ」と感じやすくなり、チャンネルへの興味へと繋がります。
2.チャンネルの世界観と方向性の統一
動画ごとのテイストがバラバラでは、チャンネル全体の印象が定まらず、ファンが定着しにくくなります。安心して見続けてもらうためには、世界観を統一することが欠かせません。
・編集テイストを揃える(BGM・カット割り・字幕デザイン)
・サムネイルの色味やフォントを統一する
・出演者やナレーターの語り口を固定する
毎回編集テイストやサムネイルのスタイルが異なると、たとえ以前見た動画が好印象だったとしても、「前回面白かったあのチャンネルの動画だ」と視聴者に認知してもらいづらくなります。
テイストを揃えることで、「チャンネルらしさ」が伝わりやすくなり、ブランドとしての一貫性が育ちます。
3.コンテンツの型(フォーマット)を設計する

毎回ゼロから企画を考えるのは非効率で、動画の内容も散らばりがちです。そこで「フォーマット」を設計しておくと、安定した投稿が可能になり、視聴者にも安心感を与えられます。
・検証型:テーマ、検証議題提示→検証シーン→結果
・知識提供型:テーマ提示 → 豆知識紹介 → 活用シーン
・比較型:AとBを比較 → メリット・デメリット提示
型を決めることで、制作の効率化だけでなく「視聴者が次に何を得られるか」を予測しやすくなり、継続視聴にもつながります。
4.サムネイル・タイトル戦略でクリック率を高める
どれだけ内容が良くても、クリックされなければ視聴は始まりません。サムネイルとタイトルは動画の入口であり、再生数を大きく左右します。
・内容が一目で分かるシンプルな表現
・感情を動かす言葉を使う(例:「やってはいけない」「知らないと損」)
・サムネイルは情報を一点に絞り、文字数を減らす
・タイトルとサムネイルで補い合い、内容を想像させる
「クリックしたくなる仕掛け」があるかどうかで、視聴数は何倍も変わります。企画段階で必ず設計しておくべき要素です。企画を考えてからタイトルサムネイルを考えるのではなく、引きがあるタイトル、サムネイルを作れるかどうかで企画を選択します。
このように、企画段階で「ターゲット」「世界観」「フォーマット」「入口設計」の4点を意識することが、動画を安定して伸ばすための基本となります。
公開後のデータ活用と改善サイクル

動画は公開して終わりではなく、データを活用して改善を続けることで成長していきます。
アナリティクスで数値を確認し、人気動画の要素を他に展開し、クリック率や視聴維持率を高める工夫を重ねます。
こうしたPDCAの積み重ねが、長く愛されるチャンネルをつくるのです。
アナリティクスで見るべき主要指標
アナリティクスは改善の出発点です。中でも次の指標は必ず押さえておきたい項目です。
・視聴維持率
どこで離脱されているかを把握し、構成や冒頭を改善する
・流入経路
検索・関連動画・外部サイトなど視聴者の入口を把握し、集客戦略に活かす
・登録者が増えた動画
ファン化につながる要素を見極め、再現性のある企画を増やす
・CTR(クリック率)と平均視聴時間
入口の強さと中身の充実度をセットで確認する
これらを継続的に追いかけることで、改善の優先順位が明確になります。
人気動画の要素を横展開する方法
再生数が伸びた動画は、その理由を分析して他の企画に応用するのが効果的です。
・視聴維持率が高い構成 → 別テーマでも同じ流れを取り入れる
・コメントで盛り上がった要素 → 新シリーズや派生企画に発展させる
・登録者増加に貢献したテーマ → 類似ジャンルを定期的に展開する
人気動画の要素を一度で終わらせず「型」として横展開することで、チャンネル全体の底上げにつながります。
クリック率・視聴維持率を改善する工夫

改善の軸は「クリックされる入口」と「最後まで見てもらう流れ」の両方です。
クリック率を高める工夫
・サムネイルは余計な情報を削り、目を引く言葉を大きく配置する
・タイトルは短くシンプルにし、サムネイルと役割分担させる
視聴維持率を高める工夫
・冒頭30秒で「最後まで見る理由」を提示する
・適度にフック(驚きや疑問提示)を挟み、飽きを防ぐ
さらに、コメントやアンケート機能を活用し、視聴者の声を次の改善に取り入れることも有効です。
PDCAを繰り返し「愛される動画」を育てる

動画運営で成果を出すには、短期的な数字に一喜一憂せず、PDCAを回し続けることが重要です。
・Plan:ターゲットやニーズに基づいた企画立案
・Do:決めたフォーマットで制作・投稿
・Check:アナリティクスで効果を確認
・Act:改善点を次の企画に反映
このサイクルを継続することで、一発のヒットに頼らず、長く愛される動画を積み上げられます。トレンドや新機能を取り入れながら改善を続ける姿勢も欠かせません。
さらに、この改善サイクルを動画ごとに回すことで、チャンネル全体が右肩上がりで成長します。言い換えれば「PDCAを仕組み化できるかどうか」が、成功する企業と失敗する企業を分ける分水嶺です。
とはいえ、「どのジャンルで戦えばいいのか」「どう改善サイクルを回せばいいのか」と悩む担当者は少なくありません。そんなときに役立つのが、株式会社仕掛人が提供する無料PDCAシートです。
PDCAを効率化する改善シートを活用すれば、YouTube運用の全体像を整理し、失敗を未然に防ぐ体制を一から整えることができます。
データを基盤とした改善サイクルを回すことこそが「動画を育てる」取り組みそのものです。まずは無料資料を参考に、仕組みづくりから着手してみてください。
PDCAシートはここから無料登録でダウンロード可能です。
成功事例に学ぶ「愛される動画」の作り方

愛される動画には共通の仕掛けがあります。
・人を通したストーリー
・親しみやすいユーモア
・最後まで引き込む構成
・悩みを解決する切り口
2つの成功事例からそのポイントを解説します。
有隣堂しか知らない世界

出典元:有隣堂しか知らない世界
ストーリー性と感情を動かす仕掛け
「有隣堂しか知らない世界」では、書店員が自ら主役となり本や文房具を紹介します。
専門知識を伝えるだけでなく、その人のキャラクターや背景が浮かび上がることで、情報は物語として届きます。
結果、視聴者は単なる解説以上の“人間味”に惹かれ、自然と心を寄せていきます。
・社員自身が語ることでリアリティと信頼感を醸成
・人柄やキャラクターがにじみ出て「この人から学びたい」と思わせる
こうした仕掛けにより、視聴者は情報よりも「語り手そのもの」に魅力を感じ、ファンとしてチャンネルに定着します。
豆知識とユーモアで視聴者を惹きつける
このチャンネルは、専門的で硬くなりがちな内容を軽やかに届ける工夫が随所にあります。ちょっとした豆知識やユーモアを交えることで、学びが親しみやすく変換され、思わず笑いながら知識を得られるのです。
視聴者は「ためになった」と同時に「面白かった」と感じられるため、繰り返し訪れる理由が生まれます。
・豆知識の提供で「役立った」という体験を積み重ねる
・ユーモアを加えて敷居を下げ、リピート視聴を促す
知識と娯楽を両立させた動画設計は、専門性を一般視聴者へと橋渡しし、広い層に支持される下地となっています。
クリエイティブの裏側

出典元:クリエイティブの裏側
最後まで“見たくなる”構成と展開
インテリアブランドの公式チャンネル「クリエイティブの裏側」では、冒頭で「NG例」を提示する構成がよく使われます。
最初に問題を見せることで「なぜ失敗なのか?」「どうすれば直せるのか?」と疑問を呼び起こし、その答えを知りたいという欲求が最後までの視聴を促します。
構成に起承転結を持たせることで、専門知識がなくても自然と理解できる仕掛けになっています。
・NG例を先に出して「なぜ?」という疑問を喚起
・解決策を提示し、視聴者を最後まで導く展開を設計
この流れは、動画を単なる情報提供から物語へと昇華させ、最後まで視聴させる強い力を持っています。
悩み解決型コンテンツで信頼を築く
さらに、このチャンネルの強みは「視聴者の悩みに直結したテーマ設定」です。家具の配置やインテリアの選び方といった生活者が抱えがちな課題を取り上げ、具体的な改善策を提示します。
視聴後に「自分に役立った」と実感できることで、ブランドへの信頼や好感が積み重なります。
・視聴者のリアルな悩みに寄り添い共感を得る
・実践的な改善策を提示し、ブランドへの信頼を醸成
課題解決をベースにしたコンテンツは、商品紹介の枠を超えて「信頼される情報源」として受け入れられ、ファン化の土台を築きます。
このように、「有隣堂しか知らない世界」は、人を前面に出し、豆知識とユーモアで視聴者を惹きつけました。一方「クリエイティブの裏側」は、NG例から始まるストーリー構成と悩み解決型のアプローチで信頼を獲得しました。
アプローチは異なりますが、両者に共通するのは「楽しさ」と「学び」を同時に提供し、視聴者に「また見たい」と思わせる力です。これこそが、動画が愛され続けるための最大の条件だといえるでしょう。
関連記事:仕掛人「【企業YouTubeアカウント】やってはいけないこと6選と改善策」
まとめ:企業が「愛される動画」でブランドを築くために

企業が動画で成果を出すためには、「売る」視点だけでなく、視聴者に楽しさや学びを与える発想が欠かせません。
ストーリー性やユーモア、悩み解決といった要素を盛り込むことで、広告ではなく“愛される動画へと変わり、ブランド好感度とファン化を同時に実現できます。
しかし実際の運用では、どのジャンルで戦うべきか、どのように改善サイクルを回せばいいかと悩む企業も多いのが現実です。そんな課題を解決に導くのが、YouTubeを中心にSNSマーケティングを手がける株式会社仕掛人です。
仕掛人は「圧倒的な結果主義」を掲げ、10万回再生以上の実績を多数持つクリエイティブ力と、データに基づいた分析力でチャンネルを成長へと導きます。特徴は「ウケる×ウレる」チャンネル設計です。
視聴者が楽しめる企画と、企業の目的を両立させる仕組みを提供します。また、投稿後のアナリティクス分析から改善施策までを一貫して支援するため、PDCAを仕組み化できる体制が整います。
愛される動画でブランドを築きたい企業にとって、まず取り組むべきは正しい戦略設計です。今の課題を整理し、一歩を踏み出すためにも、お気軽にご相談ください。
成果を生み出す具体的な一手が、そこから始まります。
まずはお気軽に、仕掛人までお問い合わせください。